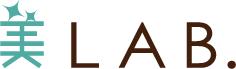「ピラティス」の効果をインストラクターが解説!継続期間やヨガとの違い
“ピラティス”と“ヨガ”の歴史

“ピラティス”の歴史
ピラティスは、約100年前にドイツ人のピラーティーズ氏が考案したエクササイズです。彼はヨガも勉強したといわれています。
第1次世界大戦の負傷兵のリハビリを担当して成果を上げ、その後アメリカに渡りダンサーやパフォーマーから絶大な支持を得たことからピラティスが広まっていきました。
“ヨガ”の歴史
ヨガは今から4000~5000年前、インドでヨガの瞑想をする人々が現れはじめたことが始まりだといわれています。
呼吸・ポーズ・瞑想を通し心・身体・精神(魂)の調和を図ることを目的として、さまざまな流派が発展してきました。
“ピラティス”と“ヨガ”の違いとは?

動き
ヨガはポーズが決まっており、そのポーズをキープしながら呼吸を整えることが多いです。
ピラティスはエクササイズの動作が決まっており、同じ動作を呼吸とともに反復し、ターゲットとなる筋肉を強化することが多いです。
呼吸の法則
ヨガは前屈など肺を縮める動作のときに息を吐き、胸を開くなど肺を広げる動作のときに息を吸う。鼻から吸って鼻から吐きます。
ピラティスは流派による違いはあるものの、力が必要なメインの動作のときに息を吐き、準備や戻る動作のときに吸う。鼻から吸って口から吐きます。
何を求めて行う人が多い?
ここではおもにアスリートを例にとって説明していきます。
ヨガは精神的な落ち着きや、精神のコントロール、柔軟性向上などを求めて行うアスリートが多いです。
ピラティスはケガからのリハビリや、体幹の筋力をつけたり、動作を繊細・正確にコントールできるようにするために取り入れるアスリートが多いです。
ピラティスの健康面での効果

内臓の機能アップ
内臓を覆うお腹のインナーマッスルを使うことで、便秘の解消など内臓のはたらきを活性化します。
身体の循環を整える
呼吸を深めて身体を無理なく動かしていくことで、肺や血液循環の機能を整え、むくみや冷えの解消が望めます。また、ホルモンのはたらきを整える効果にも期待ができます。
内臓の下垂を予防
ピラティスでは内臓を覆うお腹のインナーマッスルを使っていきます。ゆるんで下垂しがちな内臓を本来の位置におさめて、尿漏れ防止にもつながります。
骨を強化する
骨と骨をつなぐインナーマッスルを刺激することで、骨に電気信号が送られます。カルシウムの沈着を促して、骨を強化してくれます。
ピラティスの美容効果とは?

お腹を引き締める
ピラティスでおもにエクササイズしていく体幹の筋肉(腹横筋)のはたらきによって、お腹が引き締まります。
姿勢改善
骨と骨をつなぐインナーマッスルを刺激するため、姿勢をまっすぐに保つことができるようになります。
O脚防止・ヒップアップ
脚を閉じて骨盤を意識して、お腹を引き締めて股関節を動かすことによって、O脚の防止やヒップアップ効果に繋がります。
身体の歪みを整える
ピラティスを続けていくことで歪んだ姿勢や筋肉のアンバランスな使い方を正し、本来のバランスを取り戻していきます。姿勢が歪んだ場所にたまりがちな脂肪や老廃物を流すような効果も期待できます。
ピラティスをどのくらい続けると効果が得られる?

ピラーティーズ氏によると、ピラティスを「10回続ければ(心が)違いを感じ、20回続ければ(身体が)見た目が変わり、30回続ければ心身すべてが生まれ変わる」という内容を話したとされています。
美宅 玲子先生の体験談
インストラクターとして、継続的にピラティスクラスのお客様を見させていただいています。
私の印象では、毎週参加されている方は3ヶ月ほど、月2回の参加の方は半年で、月1回だけの参加でも1年ほど続けると、身のこなしが良くなり、体幹が安定して引き締まるように感じます。
ピラティスで嬉しい効果を感じよう!

ピラティスを日常的に取り入れることによって、今回ご紹介したような嬉しい効果が望めます。
ぜひこの機会にピラティスに挑戦するだけでなく、ピラティスの歴史を感じながら身体をほぐしてみてください。
- 執筆者:
- 美宅 玲子